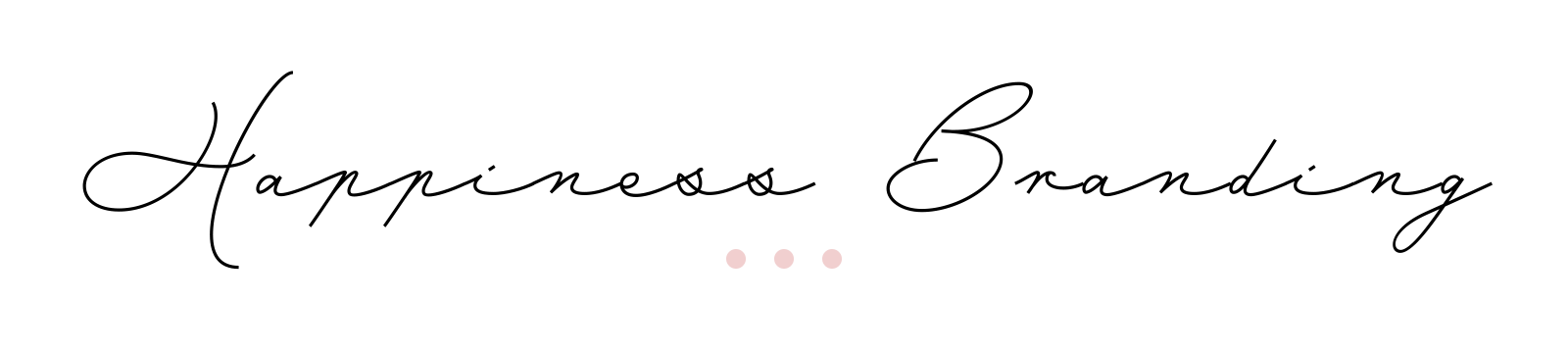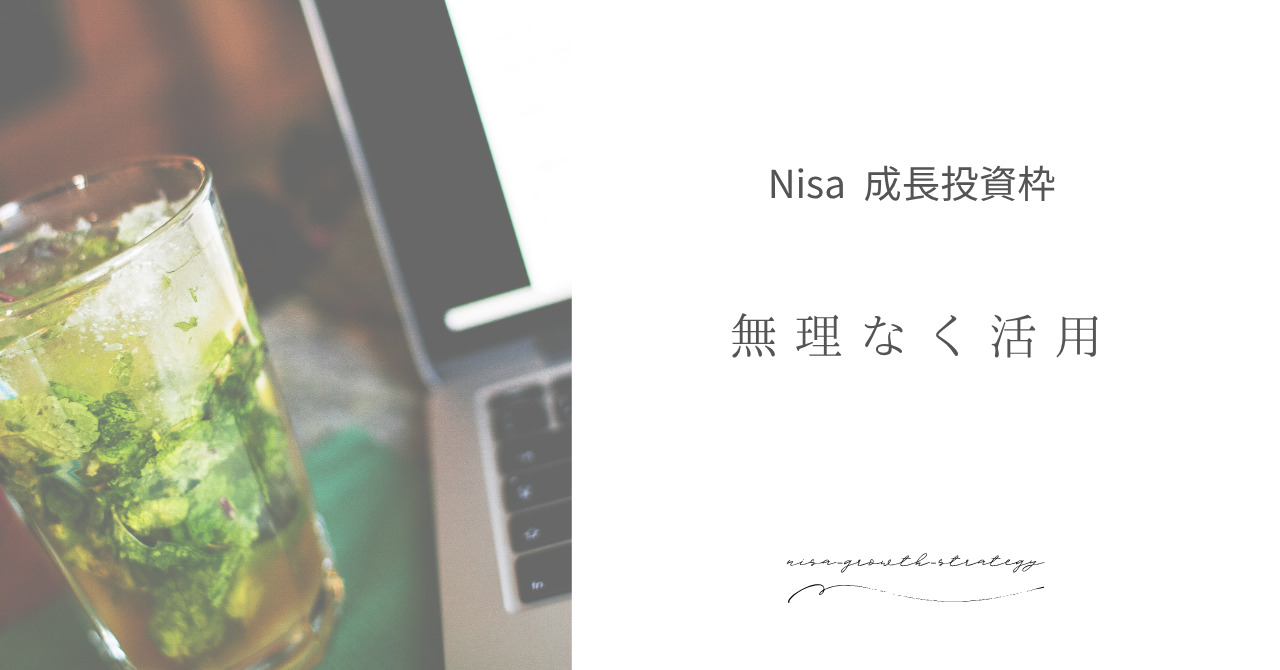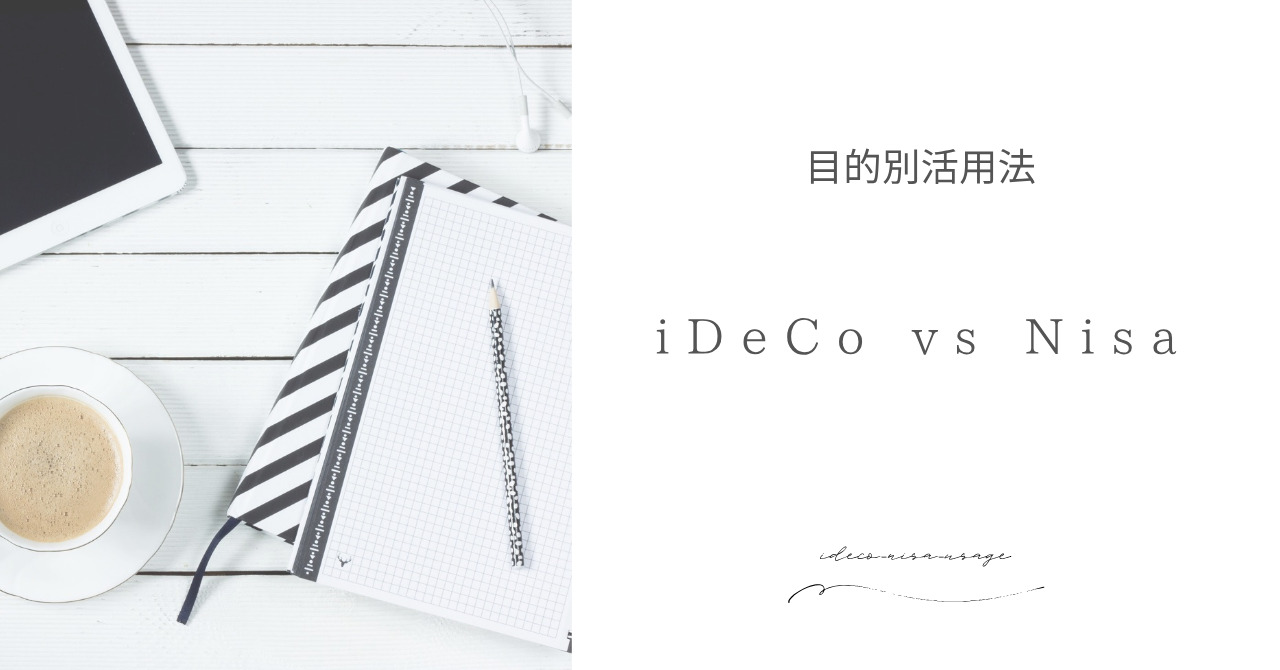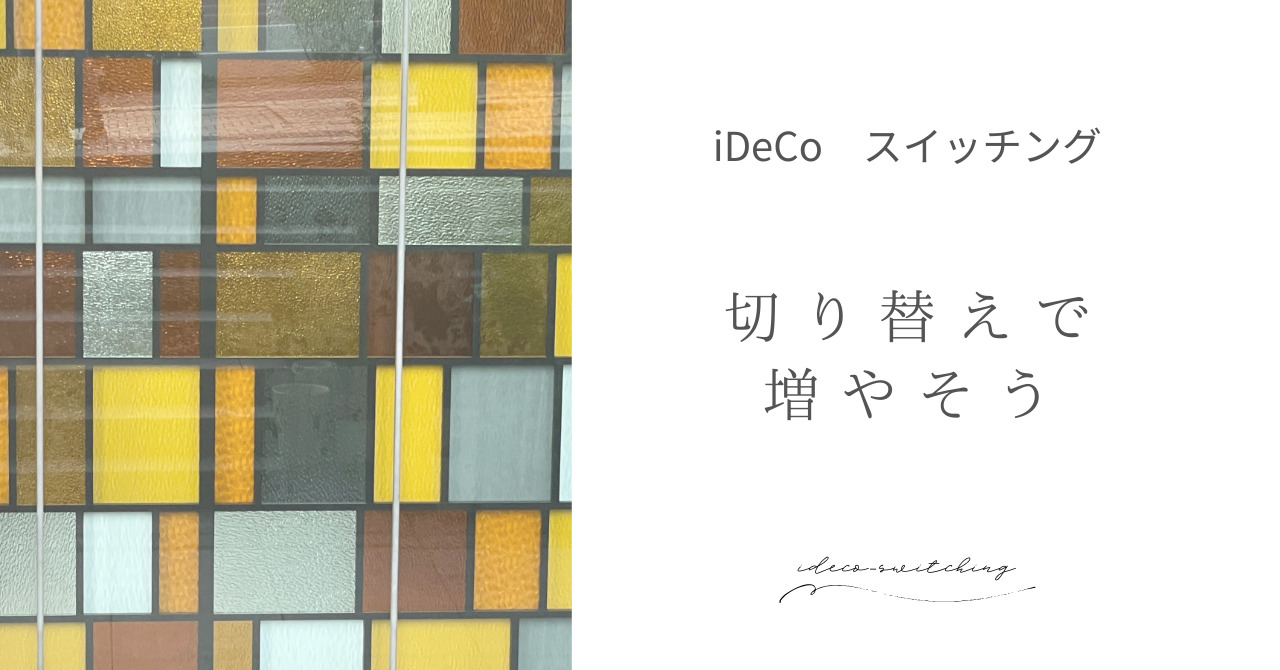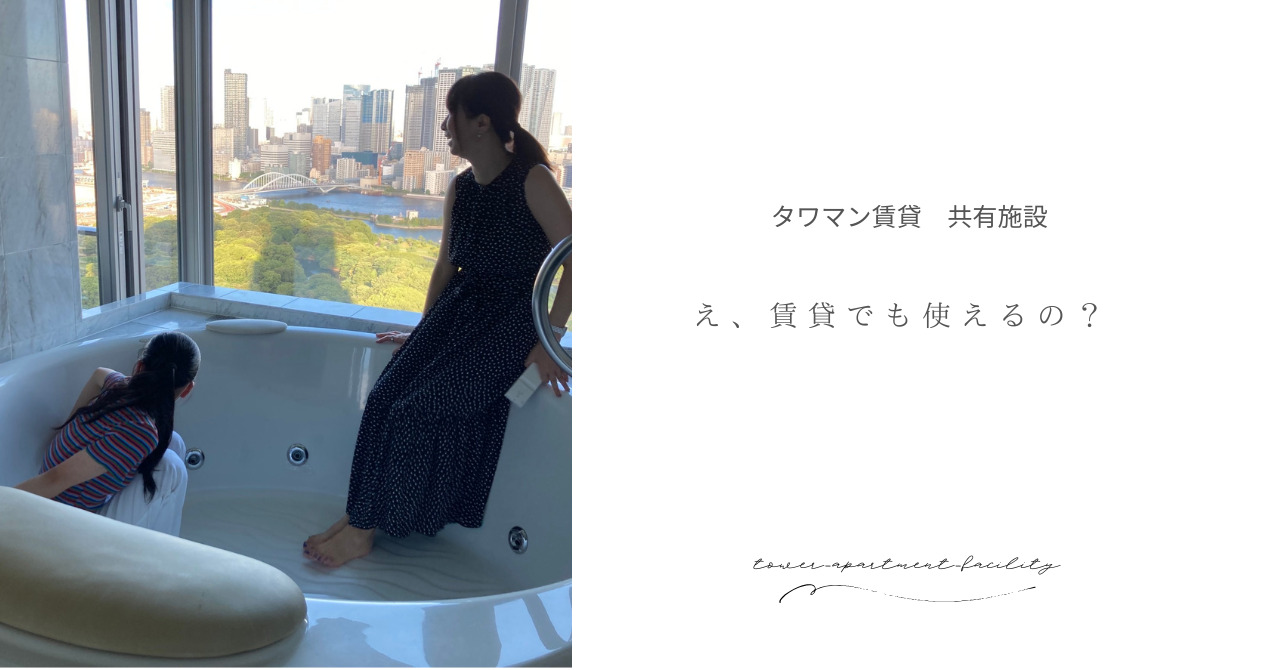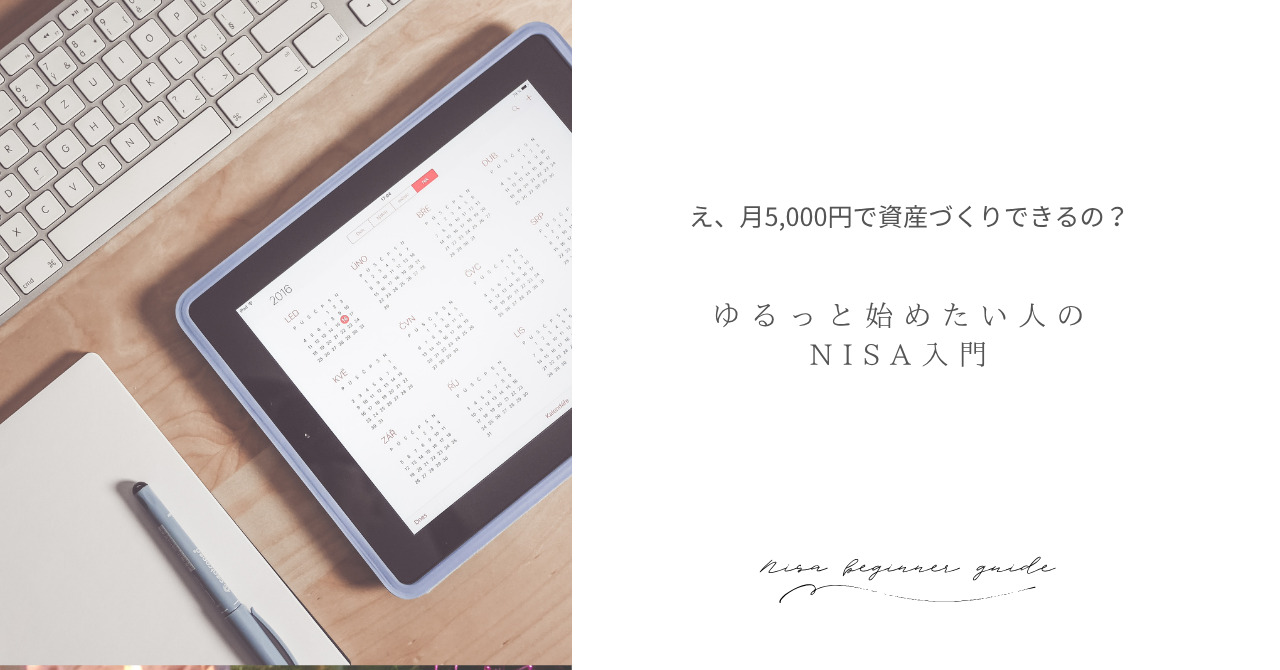「新NISA、満額使ってる人ってどれくらいいるんだろう?」
そんな疑問に答えるため、日本証券業協会などの信頼性ある調査をもとに、成長投資枠の平均利用額や利用実態を調査しました。実は「満額投資」をしている人は少数派。多くの人が“無理なく使う”というスタイルで成長投資枠を活用しています。
この記事では、新NISAの成長投資枠について、実際の平均投資額や利用傾向、無理なく使いこなすための戦略をわかりやすく解説していきます。
成長投資枠を“満額使っている”人は少数派
新NISAの年間非課税投資枠は合計360万円、そのうち成長投資枠が240万円です。
しかし、オカネコの調査によると、実際の成長投資枠の平均年間利用額は約116万円にとどまります。
また、つみたて枠についても月平均6万円台(=年間約78万円)と、
最大枠(120万円)に届いていない人が多いことがわかります。
つまり、多くの人は全体の非課税枠360万円に対して「50〜60%程度の利用」に留めているのが現状です。
成長枠を無理に埋めるべきでない理由
① 家計とのバランスを崩しかねない
日本人の平均年収は約443万円(国税庁「民間給与実態統計調査」)。
生活費や教育費、住宅ローンなどを考慮すれば、年間240万円の追加投資は現実的ではない家庭も多いはずです。
② リスクが比較的高い商品が多い
成長投資枠では、個別株や高ボラティリティな投資信託など、つみたて枠よりもハイリスクな商品が対象になるため、慎重な判断が必要です。
③ 制度の理解が進行中
新NISA制度は導入から間もないため、制度の仕組みや運用方法について試行錯誤している投資家が多いのが実情です。
データが示す「成長投資枠の使い方」3選
1. 余剰資金でのスポット購入
調査では、成長投資枠を満額活用している人は少なく、必要に応じて使う柔軟な運用が一般的です。
生活費に余裕が出た月や、特別な収入があったタイミングでスポット的に購入する形が、家計に負担をかけずに非課税枠を活用する方法として有効です。
2. 値下がり時に分割購入
株価や基準価額の下落タイミングで、少額ずつ複数回に分けて買い付けるスタイルは、今も広く行われています。
これは、ドルコスト平均法の応用として、精神的にもリスクコントロールの意味でも有効な戦略です。
3. つみたて枠との組み合わせで銘柄を選ぶ
つみたて投資枠で選んでいる投資信託と同じ銘柄を成長投資枠で追加購入することで、ポートフォリオの分散と管理の効率化が図れます。
逆に、成長枠ではテーマ型・インデックス型など“攻め”の投資信託を選び、チャレンジ枠として使う人もいます。
成長投資枠を使うときの注意点
- 生活資金を使わない:投資は余剰資金で行うのが原則です。
- 値動きに一喜一憂しない:長期視点での運用が基本となります。
- 制度変更にも注目:投資可能商品や非課税期間など、制度の見直しにも注意が必要です。
結論:「使い切らない戦略」が主流
調査結果からも、成長投資枠は必ずしも満額使い切る必要はなく、**“自分のペースで、必要なときに、無理のない範囲で使う”**という姿勢が大多数の投資家に共通していることがわかります。
新NISAの魅力は、非課税枠の大きさだけでなく、その柔軟性にもあります。
ライフスタイルに合った“ちょうどいい活用法”を見つけることが、長く安心して資産形成を続ける鍵になるでしょう。