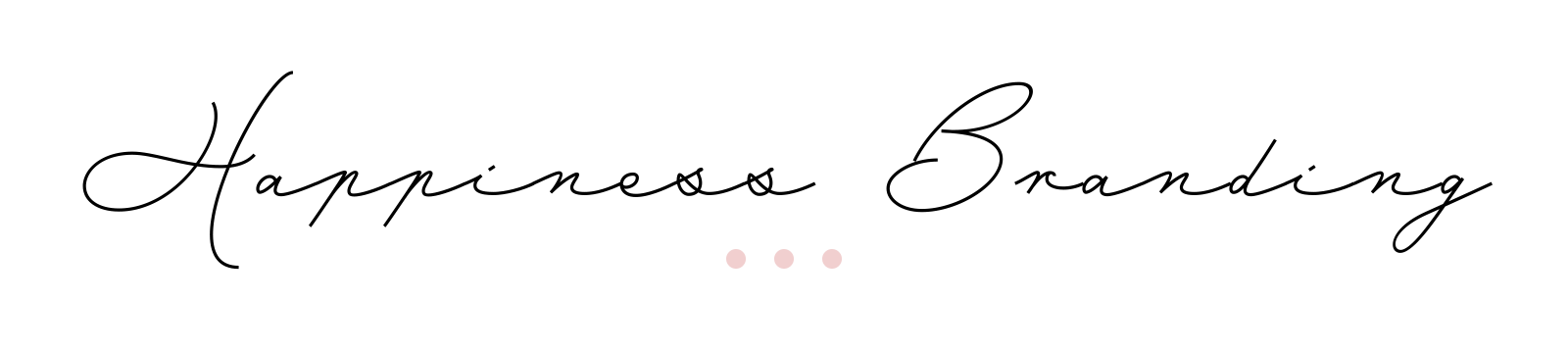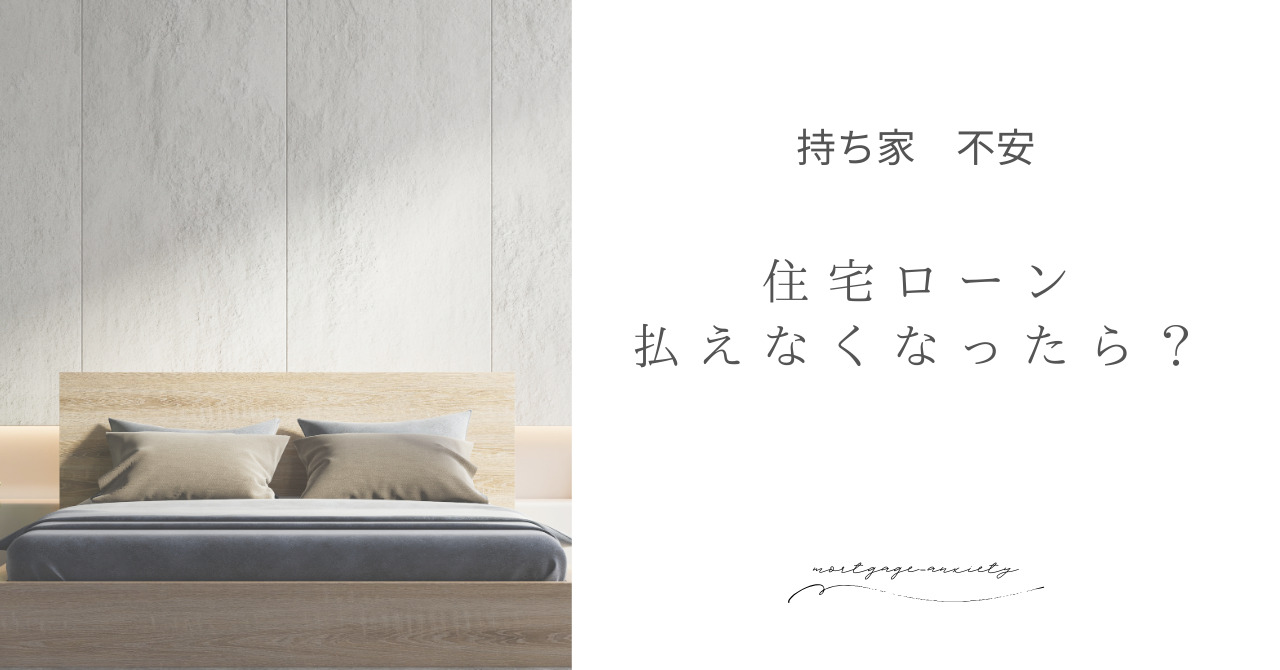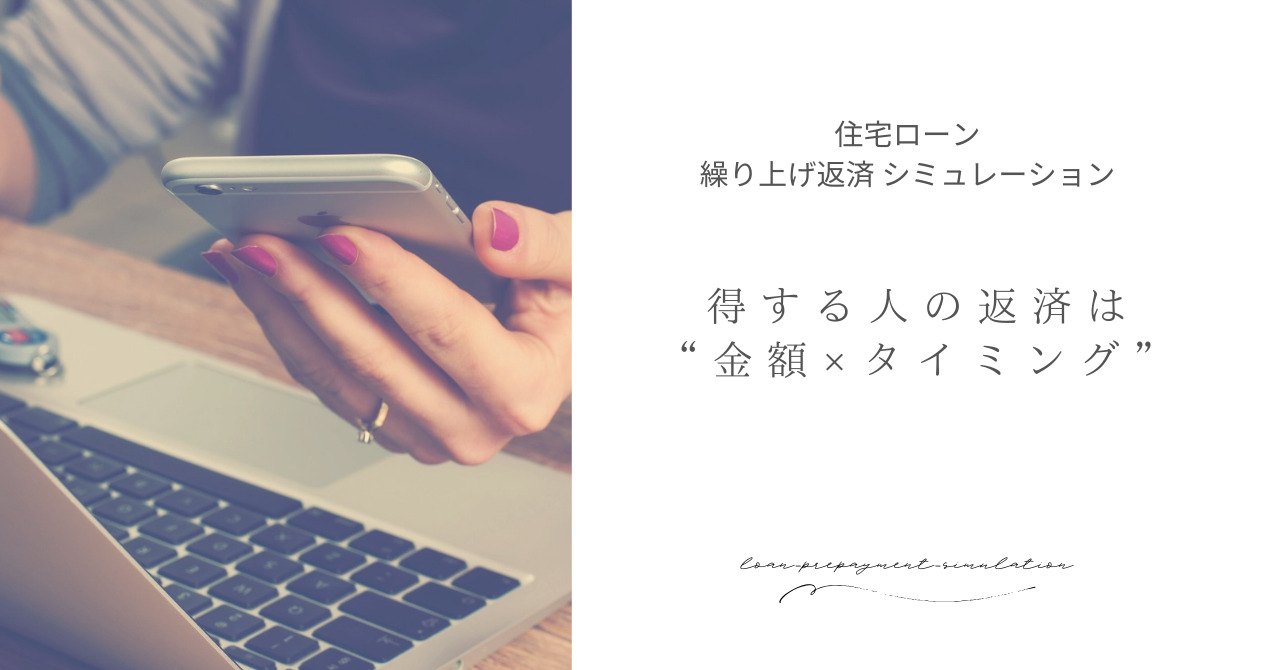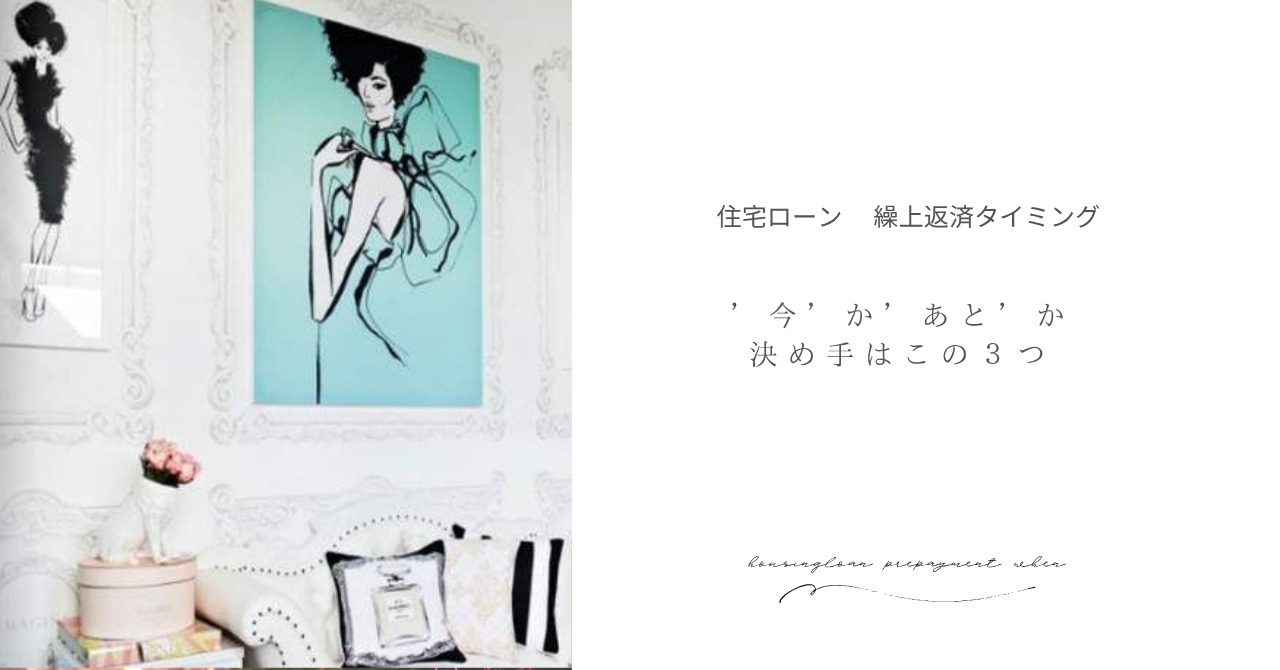住宅ローン控除、知ってはいるけれど自分が本当に対象なのか不安…。
そんな声をよく耳にします。
実際、年末残高の0.7%が戻るこの制度はとても大きな節税効果がありますが、面積・性能・年収などの条件をひとつでも満たさなければ利用できません。
私も専有面積40㎡未満の物件を購入し、制度の対象外に。
資産形成を目的に選んだとはいえ、控除が受けられないことでキャッシュフローに差が出る可能性を痛感しました。
2025年からは控除条件がさらに厳格化され、対象外になる人も増える見込みです。
この記事では、最新情報と控除額のシミュレーション、そして制度を“資産形成に活かす3つの戦略”について整理します。
2025年、住宅ローン控除はどう変わる?
2025年から住宅ローン控除は、これまでより条件が厳しくなります。
控除率は0.7%のまま据え置きで、新築は13年・中古は10年の控除期間も維持されます。
ただし、省エネ基準の適合が必須化され、所得制限も引き下げに向けて調整中です。
また、住宅の性能区分によって借入限度額が見直される一方で、子育て世帯などへの優遇措置は引き続き継続されます。
以下で、それぞれの変更点を詳しく解説します。
控除率と期間はこう変わる(2025年最新)
住宅ローン控除の控除率は0.7%で据え置き、新築は13年・中古は10年の控除期間が維持されます。
ただし、2024年以降に建築確認を受けた住宅は省エネ基準の適合が必須となり、対象外になるケースもあります。
性能区分ごとの借入限度額が見直され、子育て世帯などへの優遇措置は引き続き用意されています。
性能区分ごとの借入限度額と最大控除額
| 区分 | 借入限度額 | 最大控除額(0.7%×期間) |
|---|---|---|
| 認定長期優良/低炭素住宅 | 4,500万〜5,000万円 | 約455万円 |
| ZEH水準住宅 | 3,500万〜4,500万円 | 約409万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万〜4,000万円 | 約364万円 |
| 省エネ基準未適合住宅 | 原則対象外 | 控除なし |
👉 例:省エネ基準適合住宅で借入3,000万円
3,000万 × 0.7% × 13年 = 273万円控除
所得制限は?年収が高い人が気をつけたい条件
現行制度では「合計所得2,000万円以下」が条件です。2025年以降はさらに引き下げられる方向で調整されており、共働き・高年収層は特に注意が必要です。
制度改正のポイントを簡単にまとめると、以下のとおりです。
<2025年制度変更の要点まとめ>
控除率は0.7%で据え置き
新築は最大13年、中古は最大10年控除可能
住宅の性能区分により借入限度額が2,000万〜5,000万円に分かれる
省エネ基準を満たさない住宅は原則対象外
所得上限(現行2,000万円)は将来的に引き下げ予定あり
制度の適用は2025年12月31日入居分まで(延長は未定)
住宅ローン控除を受けられない、よくあるケース

住宅ローン控除は誰でも自動的に受けられる制度ではありません。
条件をひとつでも満たさなければ対象外になります。
特に「面積」「築年数」「省エネ性能」「年収」は落とし穴になりがちです。
購入後に対象外と気づき、制度を活用し損ねる事例が少なくありません
国土交通省によると、2024年以降に新築住宅では省エネ基準適合が必須となりました。
詳しくは国土交通省|住宅ローン減税制度の概要をご確認ください。
面積要件:40㎡未満は対象外(登記簿面積)
専有面積40㎡以上(登記簿面積で判断)が必要です。
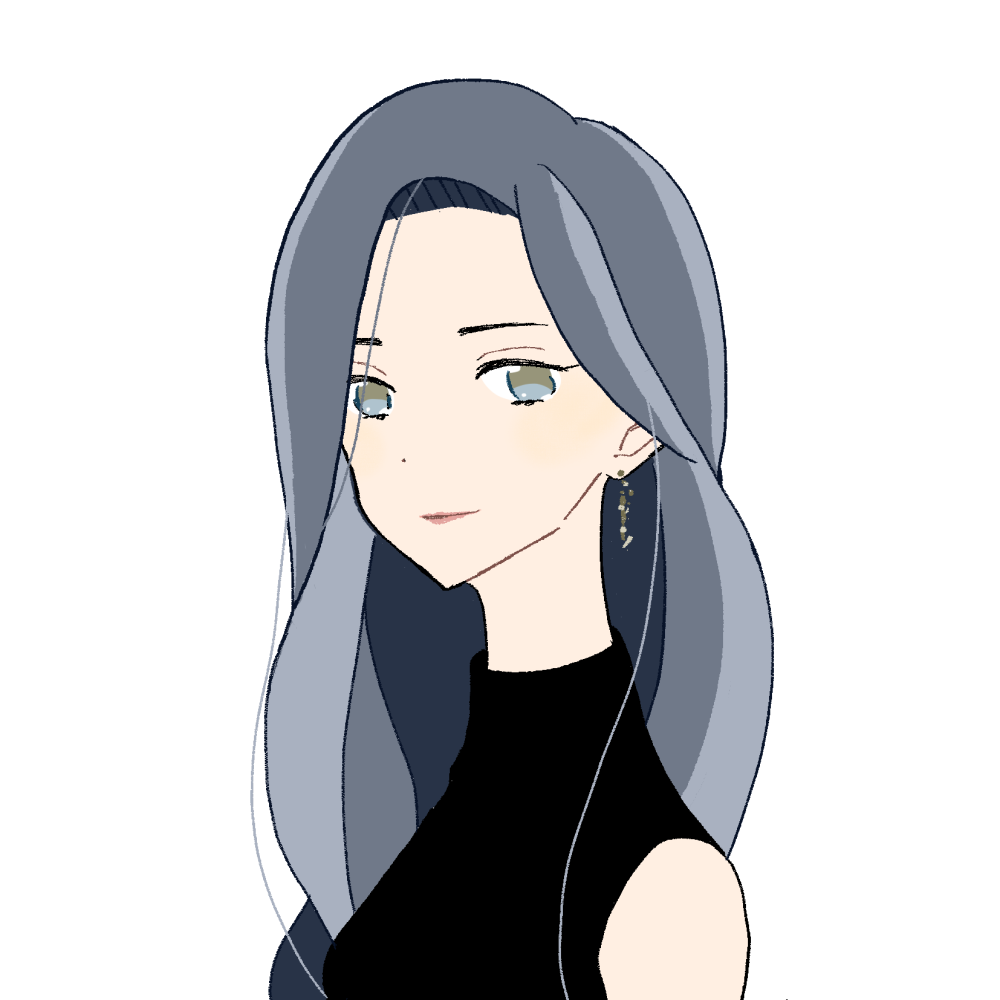
私が今回購入した物件は40㎡未満だったため、控除の対象外となりました。
購入時には資産形成目的を優先したものの、後から振り返れば「受けられなかったこと」が大きな差になると痛感しました。
築年数と耐震基準:証明書があれば対象になる場合も
木造は20年以内、マンションは25年以内が原則。
ただし耐震基準適合証明書があれば対象になるケースがあります。
省エネ基準:証明書がないと対象外になることも
2025年以降、省エネ基準に適合しない住宅は原則対象外。
中古住宅でも省エネ性能証明書が必要になる場合があります。
年収上限で対象外になるケース(共働き・高年収は注意)
所得制限を超えると対象外。夫婦でペアローンを組む場合も要注意です。
住宅ローン控除でいくら得する?シミュレーションと計算方法
控除額はこう計算する(年末残高×0.7%)
控除額は 「年末残高 × 0.7% × 控除期間」 で算出します。
ケース別の控除額シミュレーション(3,000万/4,000万/5,000万)
- 借入3,000万円(省エネ基準適合住宅)
→ 3,000万 × 0.7% × 13年 = 273万円控除 - 借入4,000万円(ZEH水準住宅)
→ 4,000万 × 0.7% × 13年 = 364万円控除 - 借入5,000万円(認定長期優良住宅)
→ 5,000万 × 0.7% × 13年 = 455万円控除
👉 毎年20〜30万円が戻る計算になります。
あなたの条件で控除額を確認する方法(シミュレーター活用)
実際の控除額は物件の性能区分や残高推移によって変わります。
まずは、住宅ローン控除のシミュレーション(イー・ローン)で、あなたの数字をチェックしてみましょう。
返済計画全体を立てたい方は、JHFのローンシミュレーターも便利に使えます。
節税を資産形成に変える3つの戦略


住宅ローン控除は単なる節税ではなく、資産形成を支える仕組みとしても活用できます。
戦略① 控除対象を意識した物件選びの視点
面積40㎡以上、立地や管理状態なども含めて「資産性が高い物件」を選ぶことが大切です。
👉 控除対象を意識することが、将来の資産価値を守るポイントになります。
戦略② 戻り分をNISA等に回して“将来のお金”に
年間20〜30万円の控除額を、つみたてNISAやiDeCoに回す。
👉 節税+投資の複利効果で、20年後の資産に大きな差が生まれます。
戦略③ 控除の申告・配分は専門家相談が安心
共働きやペアローンは控除申告が複雑になりがちです。
👉 不安な場合は税理士やFPに相談してみましょう。
まとめ|住宅ローン控除は節税から資産形成へ
2025年の住宅ローン控除は、省エネ基準や所得制限の強化によって「得する人」と「損する人」の差が大きくなります。
制度を「知っている」だけでは不十分です。
- 対象になるか条件をセルフチェックする
- 実際にいくら戻るかシミュレーションする
- 控除額をどう活かすか戦略を立てる
この3つの戦略を立てておくと、後悔を減らし安心につながります。
時代が変われば制度も変わります。
だからこそ“いまの制度”を活かし、節税を資産形成へつなげる視点を持つことに大きな価値があるのです。